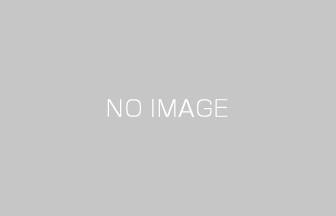どこか不器用で、どんくさくて、けれど、仕事にも恋にも必死に立ち振るまう姿そのものになぜか愛嬌がある。
恋という感情は、誰もが体験をし、高揚感を得、失意の底で人を惑わし、ぐるぐるとめぐりながらも生きてる心地のする永遠のコンテンツのように思う。
思うようにいかなさ、すれ違い、当然、自分以外の他人の感情なんて、どこまでも正確にはわからないけれど、それを慮ったり、察知したり、探ってみたりすることに恋の醍醐味が潜んでいる。
むしろ、うまくいかないからこそ、学びがあり、改善があり、次の恋にも役立てる。
さらには決していいものばかりではないけれど、記憶を、思い出を、ゆたかにしてくれる。
ひとりの世界、ふたりだけの世界、他のだれも知りえない秘密の時間は、どんな権威でさえも及ばないほどに尊いもの。
真夜中にはそんなメタファーが込められている気がした。
ー
文体で特徴的だったのは、むずかしくない漢字でもあえてひらがなで表現していたところ。
ひらがなにすることで言葉はやわらかく、そしてやさしくなる。
漢字過ぎても、ひらがなすぎても文章は読みにくい。
主人公のキャラクター設定からくる雰囲気なのか、そのバランス感覚がきれいだと感じた。
小説は確信的な言葉を、あえて遠回しに、あえて比喩的に表現したりする。
そういう文章に出会えたとき、こんな言い回しができるのかと驚くとともに、その奥行きの深さ、表現の美しさに感銘を受けることに小説のおもしろさがある。
物語の進行はもちろんのこと、著者の文体に注意が引かれる一冊だった。