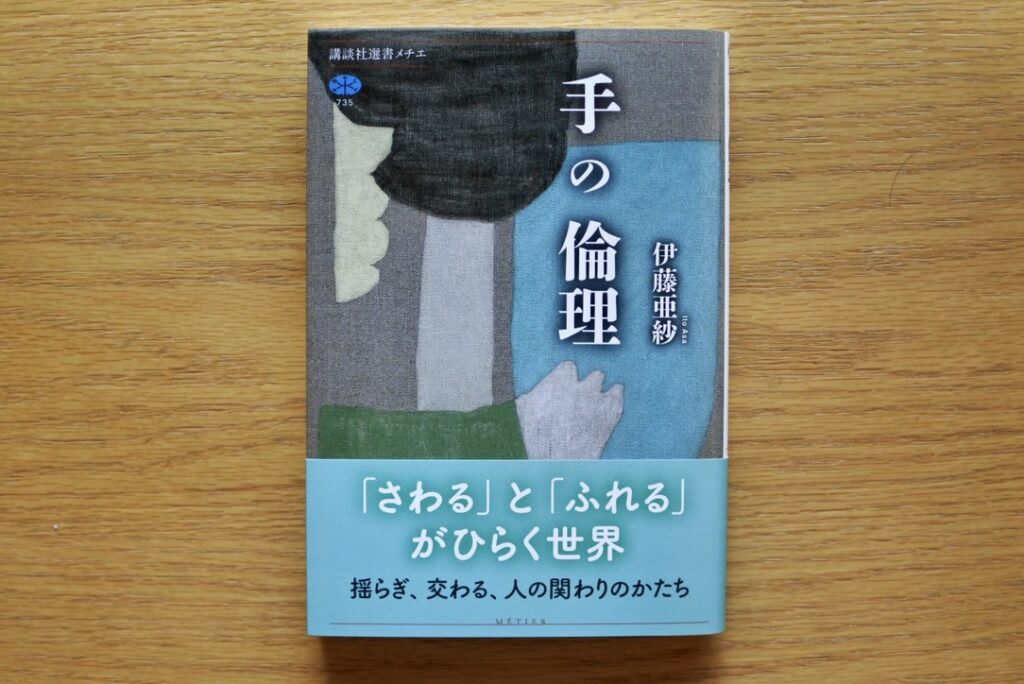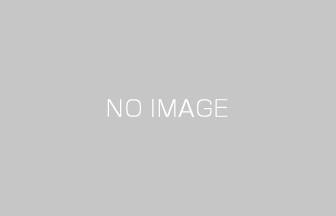人間の五感の中でも味覚と触覚は対象物との距離が近い。
直接的で、感覚的で、頭だけで理解するのでなく身体性も伴う。
職人と呼ばれる芸術の類いは往々にして身体性が重要な要素になっている。
手を動かして作るという行為の中には、頭だけでは理解できない領域が存在する。
自転車も車の運転も実際にやってみないと乗れるようにはなれないし、レシピ本を見てもその人が作る味と同じにならないのもそんな理由からだと思う。
スポーツをしている人が理論よりも小さな差異を身体でおぼえているように。
言語にする前の感覚のようなもの。
言葉の記憶よりも、身体の記憶が教えてくれること。
人間はつくづく不思議な生きものだ。
懐かしい音楽を聴けば過去のシーンが立ち上がってくるように、本棚に並んだ背表紙を見てはそれを読んでいた頃の思い出が蘇ってくるように、なんとなく説明のできない何かに支配されているような身体性は誰もが経験したことあるはず。
この身体性という視点で物事を見れば料理とも密接に関わっていることに気づく。
少なからず料理という仕事に従事してきて、日々いろんな道具に触れてきた。
例えば包丁という道具の目的は食材を切ることだけど、柄を握る力の入れ方や材質の質感、動かし方のリズム、食材によっては刃先に意識を向けたりと、経験によってでしか導かれない自分なりの記憶が手に刻まれている。
包丁以外にも、鍋やボールやトングなどの道具があるのはもちろん、手でつまむ塩の振り方や火の通り具合を確認する指の弾力加減は、まさに言葉では説明のできない身体を使ってでしかわからないこと。
道具を介した手と料理の関係は考えてみると実に奥が深い。
画面にタッチすることが多くなった現代社会において、身体を通して感じることのできる質感が奪われているような気がする。
ペンを持たずに文章や絵が書けたり、デジタル上で本が読めたり映画が観れたりと、身体との距離ができつつある。
たとえ仕事は身体から離れたとしても、趣味か何かで身体性に関わっておくことはとても重要なことだと思えた。
少し料理から離れてはいるけど手はまだその質感をおぼえている。