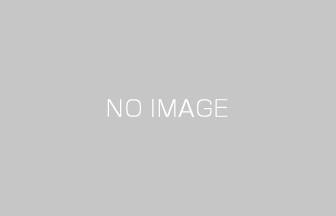好きなことをして生きよう、自分の人生を生きよう、という風潮は時代背景がよく表れている。
長生きはするし、国は守ってくれないし、会社もいつまで続くかわからないし、不安定で不確かな時代はもうすでに始まっている。
当たり前に自分の好きなことをして食べていけることは最高に幸せなことかもしれない。
でもそんな理想を叶えられる人はごくごく一部の人だろうし、そもそも好きなことだけが人生の100%という状態はありえないのではないか。
人は誰しも好きなこと2割、好きでないこと8割がデフォルトだと思っていた方が楽なんじゃないかと思ったりする。
キラキラしている人たちの見えてる部分はほんの一部にすぎなくて、人気商売もアンチとの戦いだし、努力の量はあまり表沙汰にならない。
収入の量に関係なくそれぞれのステージでみんなそれなりに悩みがあるのが社会の構造としてあると思う。
ただ好きでないことも解釈次第なので最終的に心の在り方が重要なんだとも思う。
好きなことに好きでないことがもれなく付いてくるとして、行き過ぎたメッセージは時に受け取り方を間違ってしまうような気がする。
言葉を扱う難しさがそこにある。
自分の人生を生きるからといって、人は社会的な生きものである以上、一人で好き勝手に生きていいわけではない。
どこかの道で必ず関わる相手がいる。
今の若い世代を見ていると、自分の人生を優先しすぎて、相手の人生の時間に対する配慮や敬意が欠けているのではと感じる場面がなくはない。
言葉だけが一人歩きしてるような気がする。
人権がどんどん個人として強くなっているような気がする。
老後も一人で楽しく暮らす方法、みたいな書籍もちらほら見受ける。
だれも守ってくれない自己責任論のようなメッセージも一人歩きしつつある。
孤立してしまう子供や老人、社会不適合な大人たち。
個人主義のような考え方が行き過ぎているのではないか。
きっと個人個人が自立した上で互いに助け合うというバランスが理想的なのだ。
行き過ぎた人権の危うさや都市化におけるあたたかみの欠如で人は幸せになれるのだろうか。
翻って、情報を遮断して僻地で暮らしている民族の方が幸福度は高いのかもしれない。