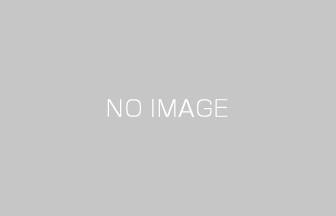料理は味以上に、食感、香り、温度など、いろんな要素で構成されている。
タピオカやキクラゲは食感だけが重要で味そのものが美味しいとは言えない。
松茸や柚子も香りを楽しむような食材。
冷たいから美味しいもの、温かいからこそ美味しいもの、と個々の料理には、どの要素の主張が強いのか、どの部分を食べているのかを考えてみるとおもしろいと思った。
フライドポテトならカリカリを食べているだろうし、イクラならプチプチを食べているだろうし、ナンコツならコリコリ、焼き餃子ならパリパリ、生パスタのモチモチなど、食感を考えるだけでも味そのものよりテクスチャーがメインとなっていることが往々にしてある。
料理を考える上でも、カリカリとフワフワを組み合わせたり、サラサラとモチモチを組み合わせたり、食感を中心に考えるみると料理においてオノマトペの存在感がよりいっそう際立つ。
香りや風味も時にメインの要素となる。
出し汁やハーブや柑橘の香りは美味しさを演出する上でなくてはならない存在だ。
このように考えていくと意外に味そのものはそんなに重要でないとさえ思えてくる。
誰と食べるか、どこで食べるか以上に、料理を分解して考えてみると見えてくるものがあっておもしろい。
たこ焼き、お好み焼きは味や食感以上にきっとソースがメインになってるに違いない。
それでいうとポン酢とかは何に合わせてもそれだけで美味しい。
うどんは、出しなのか食感なのか味なのか、一体どの部分を大事にして食べているのだろう。
もちろん人によって好みが違うので一概には言えないけれど、そんなふうに考えながら料理を楽しむと探究する余地があると思えた。