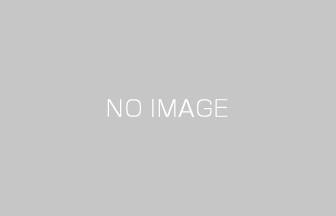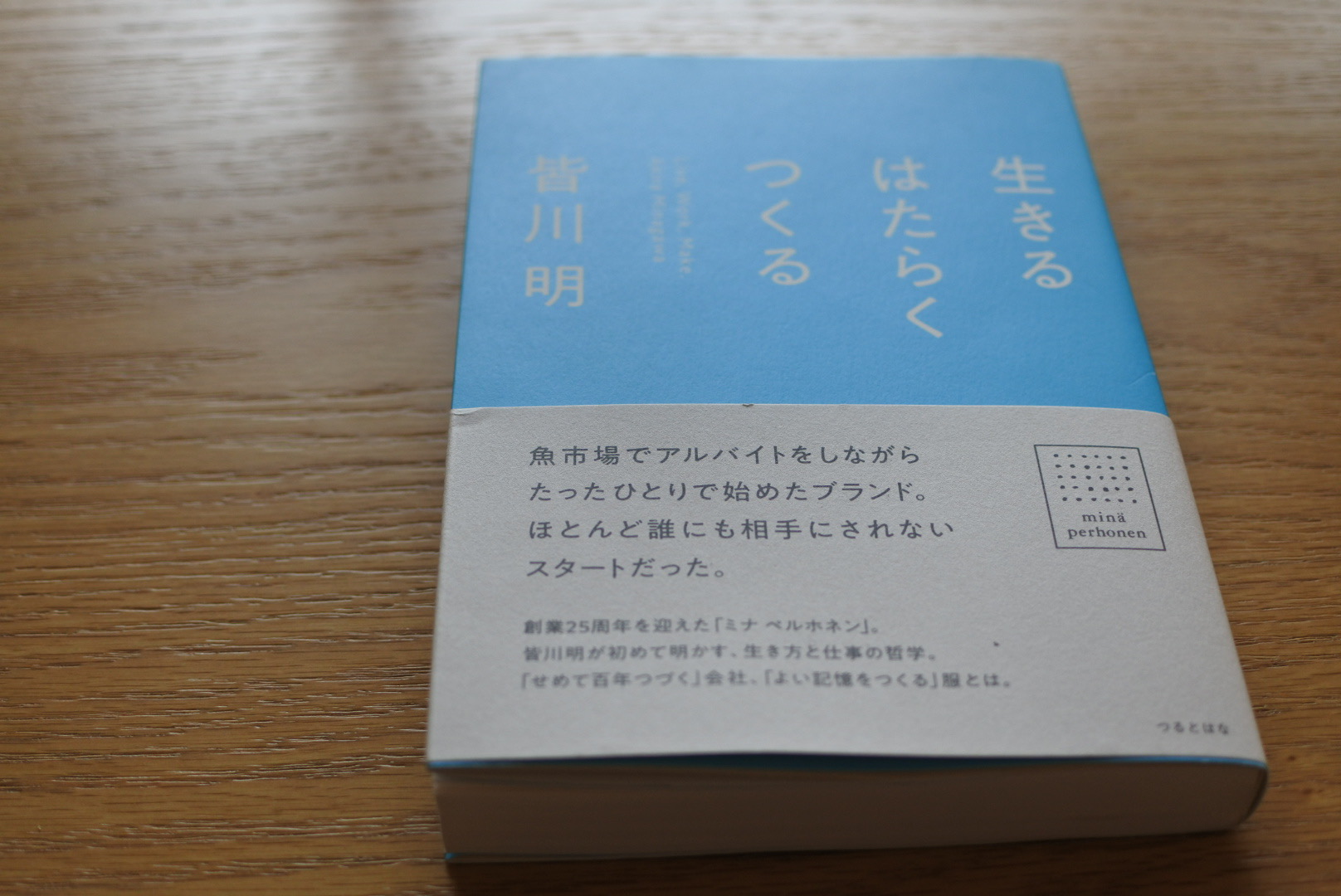昨日の気づきからあらためてお弁当について考えてみたくなった。
概念としては「携帯できる食事」という要素が大きい。
お弁当の起源を辿ってみても、大勢で食べれること、便利であること、好都合なこと、から生まれている。
いつでもどこでも美味しく食べれる、がおおよそお弁当のキャッチコピーだろうか。
蓋を開けるまでの何が入っているかのワクワク感や、いろんな種類のおかずを味わえるといった楽しさがあるのは、ただ便利なだけではなくお弁当ならではのよさかもしれない。
なのでそんなお弁当の本質に合わせるように、適した料理を考えることが決まり事になってくる。
特長というか、条件というか、制約をいくつか。
・いたみやすいものを入れない
お弁当の最大のリスクは食中毒。
作り手の手から離れたらいつどこで食べるかはお客さま次第だけど、もし何かあった場合はやはり責任が伴うので、当然生ものは扱えない。
・味や状態に変化がないもの
時間が経って味や状態が大きく変わるものは扱えない。
麺類や汁物はもちろん扱えないし、動物性の脂が冷めて固まるのも避けたいところ。
和え物やマリネでも素材から出る水分は逆算してコントロールしないといけない。
・温度や匂いの管理
例えばごはんが熱々のうちに蓋を密閉してしまうと中身全体が蒸れてしまって状態が悪くなる。
また匂いのきついものが一つあるだけで他のおかずにも移ってしまう。
などなど注意を払うべき事柄が多々あって、できいることがけっこう限られてくるのがお弁当の難しいところ。
同じようなメニューでは、お客さまの飽きにもつながってくる。
それでもそれこそがお弁当というみんなの総意なので、その中でうまくやりくりするしかないのだが。
期待値は各個人によって違うだろうけど、歴史的文脈から見てもお弁当というのは、いつでもどこでも常温でも美味しく食べれて楽しめるもの、というひとつの料理のジャンルとして確立していると言えるのではないでしょうか。
フランス料理、イタリア料理、お弁当料理、というように。
だとしたら、そもそもうちは何屋さんなのか?という問いから始めないといけない。