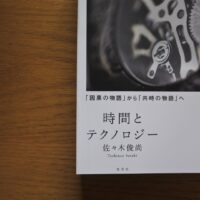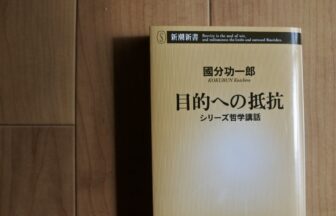明日起こる出来事はなんとなくわかるけど、10年後に世界がどうなってるかなんて誰にもわからない。
もしも10年後の世界が今わかるとしたらどう思うだろう。
たとえハッピーな結果だとしても、きっと今がおもしろくなくなると思う。
アンハッピーな結果だったら今から辛くなってしまう。
いずれにしても、何でもわかりすぎると人生は退屈になる。
それでも人はこれからどうなるかをわかりたいと思う。
学んだり、体験をしたり、占いをしたり。
わかるの語源は「分かる」と書くように、知識が分岐して隅々まで行き渡っているというイメージからきている。
天才たちの叡智が世界の真理を次々に明らかにしているのに、まだまだわからないことばかり。
哲学分野では、ああでもないこうでもない、と数千年ずっと言い合っている。
わからないことをわかりたいと思う気持ち、それこそが知的好奇心というやつで、これは人間だけに与えられた特権だと思う。
その作業にこそ意欲やエネルギーが生まれ、人間を中心とした文明をここまで豊かにしてきた。
未来が事前にわかってしまったらおそらく今の世界は存在していない。
ああでもないこうでもない、と言い合うことが人と人のコミュニケーションを生んでいる。
考え方の違う人がいるからこそ互いに切磋琢磨し合う。
全人類の思想が一律だと思うとそれはもう恐ろしい。
未来をわかることがむずかしいことだとして、過去はどうだろう。
人間の記憶には限界がある。
忘れる、という機能は悪い面で語られがちだけど、悲しみや苦しみは忘れる機能があることで次に進むことができる。
これもある意味で意欲やエネルギーが生まれ、次をもっとよくしようと行動するためには必要な機能だと思う。
ところが過去に関しては、データとしていつでも引き出せるようになったので、忘れることが許されなくなってきている。
過去の不祥事が今の活動に影響を与えるようなことも起きている。
信用スコアたるもの人生の行動履歴をすべて数値化しようとする動きで、忘れることができないというのは長い目で見て人類の損失にならないのだろうか。
悪いことができない、失敗ができない、という環境は、同時に挑戦する機会を奪っているのではないだろうか。
そうなると誰かの手によって人間が完全に統率されてしまう。
これから世界はどうなっていくのか。
わからないからおもしろい。
極めようとする過程に極める本質があるのかもしれない。
それは未来や過去(解釈)を変えれる余地が与えられているということ。
希望があるからこそ今をがんばれる。